日本は地震や台風、豪雨、土砂災害など、自然災害が多い国です。
突然の災害に見舞われたとき、大切な家族の一員である猫をどう守るか、普段から考えておくことは非常に重要です。
過去に起こった震災では、多くのペットたちが取り残され、飼い主と離れ離れになってしまいました。
また、避難所に一緒に連れてこられた猫も、動物アレルギーを持つ人や動物が苦手な人と同じ空間で過ごさなければならず、トラブルやストレスを抱えながらの生活を強いられたようです。
災害時には人命救助が最優先となり、行政機関はペットまで十分に支援することが難しいのが現実です。
そのため、ペットフードやトイレ用品なども避難所に届くのは遅れがちです。
だからこそ、「猫を守れるのは飼い主だけ」という意識を持ち、事前の準備が欠かせません。
今回は「猫と防災」をテーマに、災害が起こったときに愛猫をどう守るかについてまとめました。
普段はのんびり過ごしている猫も、災害時には思わぬストレスや危険にさらされることがあります。
大切な家族である猫の命を守るために、どんな準備が必要か、一緒に考えてみましょう。
災害時に備える!猫の防災グッズについて
いざという時に混乱しないよう、防災グッズはあらかじめ優先順位をつけて備蓄しておきましょう。
重すぎるものやかさばるものは避け、まずはすぐに持ち出せる必需品をまとめておくのが基本です。
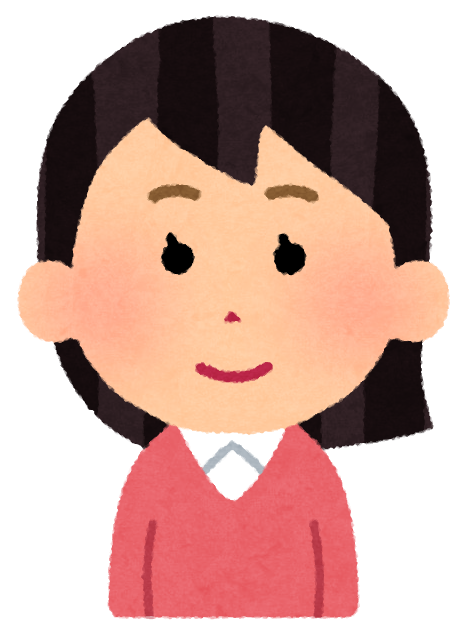
重要度によって3段階に分類しましたので、確認してみてください。
優先順位1位:命を守るための必需品
フードと水


最低5日分、可能なら7日以上用意しましょう。普段と同じフードを用意すると食欲不振を防げます。
また、ウェットフードよりもドライフードのほうが、かさばりにくいためおすすめです。
水は猫専用のものではなく、人と共用で問題ないかと思います。
薬・療法食
持病や食事療法中の猫には欠かせません。
動物病院が閉鎖しても困らないように準備しましょう。
キャリーバッグ・ケージ
避難時は必ずキャリーバッグへ。リュックタイプであれば両手が空くので便利です。
避難所では放し飼いにはできないため、ストレス軽減のために折り畳み式ケージもあればベストです。


トイレ用品
使い慣れた猫砂を用意しましょう。
トイレ環境が変わると我慢して体調を崩す子もいるので注意してくださいね。
ハーネス(リード付)
猫は小さな隙間からでも逃げられるため必須です。
普段から装着に慣らしておきましょう。
食器
折りたたみや軽量タイプが便利です。
優先順位2位:猫と飼い主をつなぐ情報
迷子札・首輪
連絡先を記載しておき、嫌がる子でも避難時だけは着用をしましょう。
猫の写真
全身が写って模様や特徴が分かるものが望ましいです。飼い主と一緒の写真もあると安心ですね。
ワクチン証明書・保険証
ほかの動物との接触に備えて必須です。コピーでも可です。
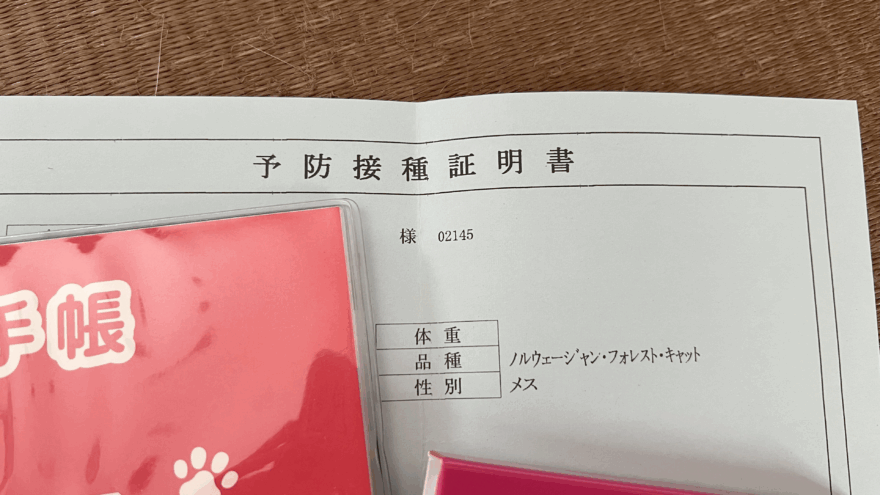
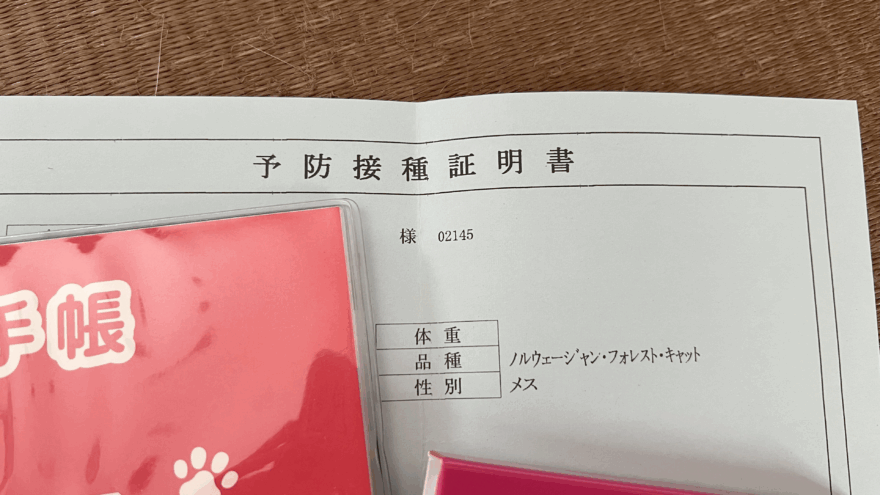
優先順位3位:避難生活を快適にするもの
ケア用品
タオル、ウェットティッシュ、ブラシなど。使い捨てのものなど、人と共用できるものでもよいかと思います。
洗濯ネット
猫を落ち着かせたり、動物病院での診察時にも役立ちます。


おもちゃ
お気に入りを用意しておくと、緊張が和らぎます。
防災グッズの準備だけでなく、平常時からの備えも非常に大切です。
次は、日頃からできる防災対策についてみていきましょう。
日頃からできる防災対策、5選


その1、住まいの防災対策
まず飼い主自身が無事であることが猫を守る第一歩。
家具の固定、落下物対策、耐震性の確認をしておきましょう。
そのうえで、猫のケージやキャリーを安全な場所に設置しておくと安心ですね。
その2、しつけと健康管理
猫は環境の変化に弱いです。
そのため、キャリーバッグやハーネスに普段から慣れさせておくと避難がスムーズにできます。
ワクチン接種、ノミ・ダニ予防などの健康管理も忘れずにしておきましょう。
その3、マイクロチップの装着
2022年6月以降、新しく迎えた犬猫にはマイクロチップ装着が義務化されています。
すでに飼っている猫でも装着を推奨されており、外れてしまう首輪や迷子札よりも確実です。
また、マイクロチップは装着しただけでは意味がないので、登録することも忘れないようにしましょう。
その4、避難所・避難ルートの確認


ハザードマップを確認し、どの避難所が猫を受け入れてくれるのかを調べておきましょう。実際に避難訓練をして、持ち出し時間や猫の反応を確認するのも有効です。
その5、家族・ご近所との連携
緊急時の連絡方法や集合場所、猫の世話の分担について日頃から話し合っておきましょう。地域の人との信頼関係が、避難所での安心にもつながります。
また、避難所に猫を連れて行けない場合もあります。
親戚や友人など、事前に複数の預け先を確保しておくと安心です。
猫の防災対策まとめ
突然の災害は、飼い主にとっても猫にとっても大きな試練となります。
しかし、事前の準備次第でその負担を大きく減らすことができます。
避難所での生活をイメージしてみること、日頃から猫が安心できるグッズや行動を確認しておくことは、決して無駄にはなりません。
防災とは「特別なことをする」のではなく、「日常を少し工夫する」ことの積み重ねです。


キャリーに入る練習をしてみる、迷子札を確認する、水やフードを買い足すなど、やれることはたくさんあります。
そうした小さな一歩が、結果的に猫の命をつなぐ備えになります。
そして何より、飼い主が冷静に行動できることが、猫にとって最大の安心材料です。
自分の身を守りながら、愛猫と共に乗り越えられるように、今日から少しずつ準備を始めていきましょう。
ただ、今回情報を整理してみたものの、実際に災害が起こったときに「本当に猫と一緒に必要なものをすべて持ち出せるのだろうか?」という不安も残ります。
いざという時は、想定以上に慌ただしく、冷静に判断するのが難しい場面も多いはず。


避難先で猫が安心して過ごせる環境を整えられるのか、十分な物資を確保できるのかなど、考えれば考えるほど心配は尽きません。
だからこそ、普段から少しずつ準備を進めたり、他の飼い主さんがどんな工夫をしているのかを知っておくことが大切だと思います。
自分では思いつかない方法や、なるほどと思えるアイデアに出会えるかもしれません。
皆さんは、もしもの時に備えてどんな工夫をしているでしょうか。
お互いの経験やアイデアを共有し合うことで、より安心できる防災対策につながると思います。
情報を分かち合いながら、猫も人も安心して暮らせる未来を一緒に築いていきましょう。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
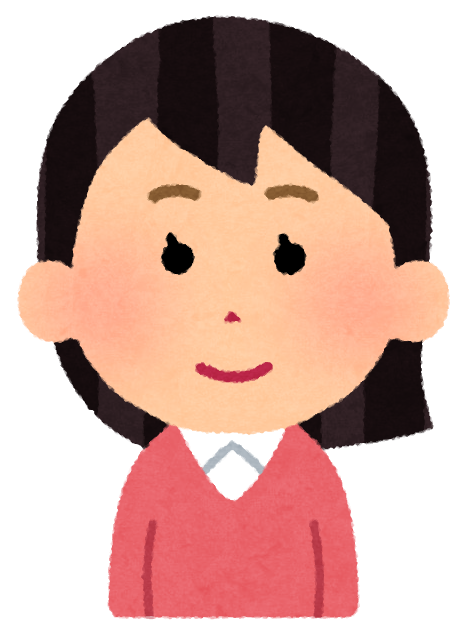
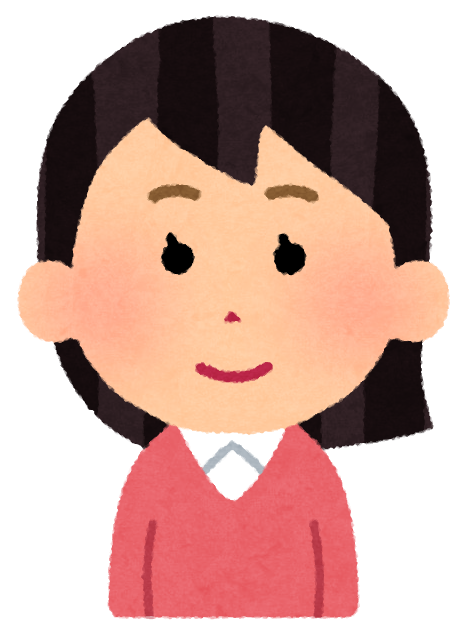
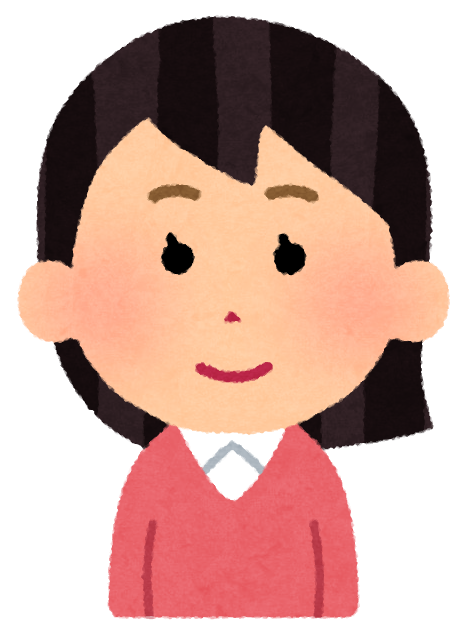
皆様の猫たちの安全のための一助になれば幸いです。
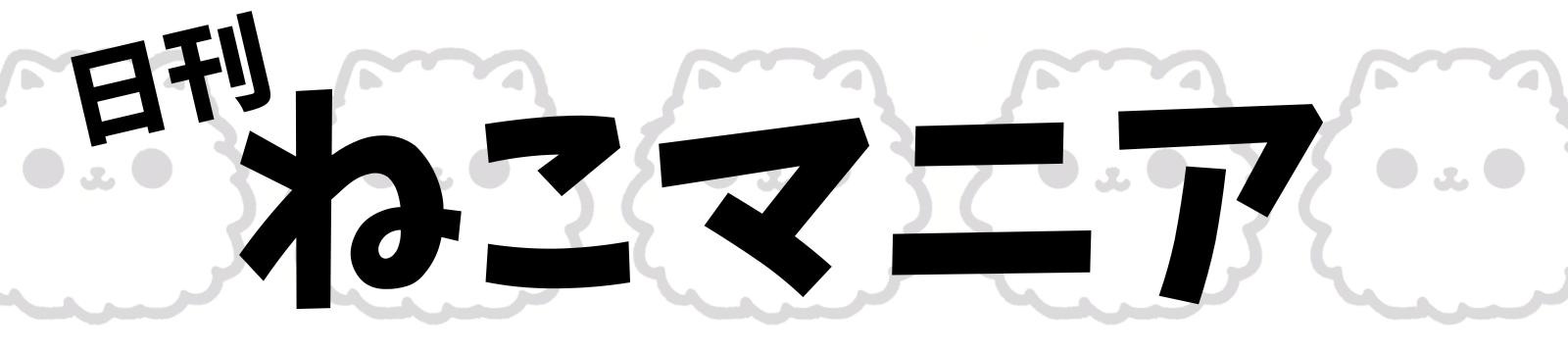





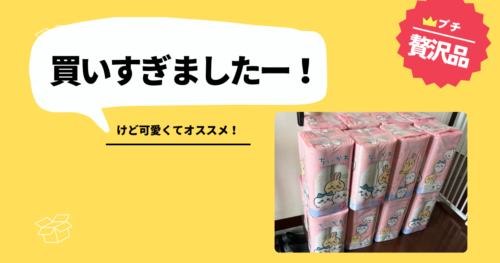



コメント